PFASってなんだろう?
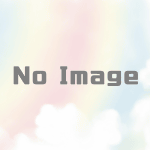
沖縄で問題になっている「PFAS(ピーファス)」という化学物質は、水や油をはじく性質を持つため、泡消火剤や防水加工、包装材などに長年使われてきました。このため便利な製品に使われてきた一方で、世界中で自然に分解されにくく、体や環境に残り ...
沖縄県・那覇市、教育委員会のメンタルヘルス対策への提言
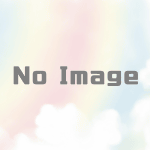
沖縄県の教職員のメンタルヘルス問題は、単なる人員不足や業務負担の増加という次元を超えた、教育制度そのものの持続可能性に関わる深刻な課題となっている。最新の文部科学省の調査によれば、沖縄県内の教職員の精神疾患による休職者数は268人、在 ...
令和8年(2026年)沖縄は選挙イヤー
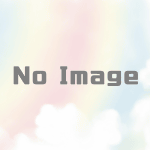
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、本年、令和8年(2026年)は沖縄県においては沖縄版統一地方選挙イヤーとなります。
戦後直後、日本では地方自治制度の再構築 ...
「ちんすこう」の名は県外ものに?!〜知的財産について
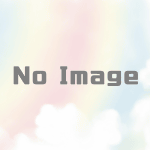
近年、日本由来の商品名やブランドが、国内外で第三者に商標登録されてしまう事例が相次いでいます。中国における日本酒の商標登録問題は、その象徴的な例です。日本国内で正当に使われ、評価されてきた名称であっても、海外では自由に使えなくなる場合 ...
沖縄が世界の架け橋となるために!航空関連産業クラスターとは
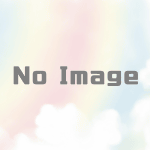
現在、那覇空港内の滑走路脇にある格納庫を利用した“MRO”とは、航空機の「整備、修理、点検(メンテナンス、リペア、オーバーホール)」をまとめた呼び方で、航空会社が安全運航を続けるために欠かすことができない基盤産業です。航空機の機体や部 ...
ベトナム北部と沖縄の新しい繋がりを探して ハノイ・ニンビン省
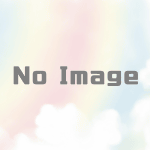
11月6日から9日にかけて、沖縄県とベトナム北部との連携の可能性を探るため、ハノイ市とニンビン省を訪れました。(初日と最終日は移動のみです、結構ハード 汗)今回の視察では、観光・企業・人材の三つの分野で、沖縄とベトナムが想像以上に共 ...
沖縄を止めないために─サイバー攻撃時代の行政BCPを再点検する
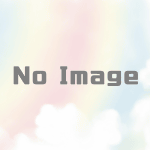
行政機関の事業継続計画(BCP)は、災害だけでなく、近年多発するサイバー攻撃を前提に考える必要があります。飲料メーカーや物流企業への攻撃では、基幹システムが一度停止しただけで、生産、物流、顧客対応といった複数の機能が連鎖的に停止しまし ...
AI発展による労働・生活環境の変化
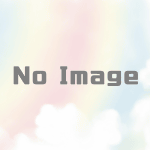
2025年11月2日(日)の NIKKEI The STYLE「文化時評」に「米国で『ブルーカラービリオネア』現象 AI発展で潤う肉体労働者」という記事が掲載されていました。
私自身も、ChatGPTやX(旧Twitter ...
首里城火災から6年 責任はいずこへ?
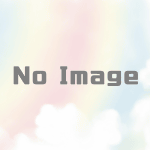
2019年10月31日未明、沖縄の象徴である首里城が火に包まれました。
正殿をはじめとする主要建物7棟が全焼し、2棟が一部焼損しました。火災発生から6年が経った現在、再建工事は終盤を迎えています。
2026年秋の完成を ...
宮古島島民遭難事件から
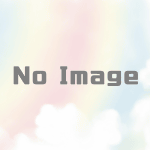
1871年11月、琉球王国領の宮古島から年貢納付船が那覇を出航し、帰途に暴風に遭って台湾東南部・八瑤灣付近に漂着しました。乗員66名(記録によっては69名とも)中、上陸後に12名が救助・帰還したものの、54名が付近に住む排湾族に殺害さ ...