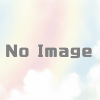高校無償化の是非と今後の課題
令和7年度予算において、高等学校の無償化が大きな議題となりました。維新の会の政策を受け入れる形で、公立・私立を問わず就学支援金の所得制限が撤廃され、公立高校は実質的に無償化されます。また、私立高校の授業料支援額も全国平均の45万7000円に引き上げられることになりました。
・自民・公明・維新の3党が2025年度予算案について、「高校無償化」を柱とする修正で合意
公立高校の無償化は教育の公平性を高める意義があると思いますが、私立高校まで含めることには疑問が残ります。私立高校は独自の教育方針を持ち、経営の自由度も高いため、公的支援を拡大することで授業料の値上げを招く懸念があります。また、私立への進学には塾費用などの追加負担も伴うため、無償化によって家庭の負担が軽減されるかは不透明です。
・日本教育新聞 令和7年通常国会質疑から【第3回】無償化と公立高校
一方で、「教育は勉強だけではない」という意見もあります。中学校の部活動の地域移行が進む中で、専門的な指導を求めて私立高校を選択する生徒もいます。しかし、経済的な理由で私立を断念せざるを得ないケースもあり、その救済策として無償化を支持する声もあります。ただし、授業料が無償化されても寮費や遠征費などの高額な負担は残り、結果として親の負担は依然として大きいままです。
また、今回の無償化政策については、そもそも税負担である以上、政策のあり方そのものを見直すべきではないかという声もあります。
高校の授業料無償化を行うよりも、同額分を全国民から減税した方が公平であり、効果的ではないかという考えもあります。現在の無償化政策では、高校に通う世帯だけが恩恵を受ける仕組みになっていますが、減税であればすべての国民が平等に恩恵を受けることができます。特に、無償化の財源を国民の税負担で賄う以上、減税によって家計の自由度を高める方が合理的なのではないかという意見もあります。
そして、高校無償化を行うならば、学校ごとに不均等な補助を与えるのではなく、最終負担者である家庭に「利用券」を配布し、公立と同額分の補助を適用する仕組みにすべきではないかという提案もあります。現在の制度では、学校ごとに異なる補助が与えられるため、公平性が損なわれる可能性があります。利用券制度であれば、公立・私立問わず同額の補助を受けることが可能となり、家庭の選択の自由が保たれると考えられます。
さらに、教育に関する予算は未来への投資であり、国債を発行して充てるべきではないかという意見もあります。教育は将来の国の成長を支える重要な投資であり、その負担を現役世代だけに求めるのではなく、世代を超えて分担すべきだとする考えです。そのため、一時的な財源不足を補う手段として国債を活用することで、長期的な視点で教育政策を進めるべきではないかとの提案もあります。
大阪では公立高校の定員割れが問題になっているにもかかわらず、この点はほとんど報道されていません。公立高校が魅力を失い、私立希望者が増えた結果、公立を希望する人が減る可能性もあります。公立の環境を改善することなく私立の支援を強化することは、教育の二極化を助長しかねません。
さらに、無償化によって外国人留学生を多数受け入れる学校にも公的資金が投入されるのではないかという懸念があります。例えば、日章学園九州国際高等学校では、在学生の9割が中国人留学生であり、校長も中国人であると報じられています。入学式では中国国歌が斉唱され、中国人民に敬意を表するスピーチが行われ、授業も主に中国語で進められているとされます。このような学校にも日本の税金で授業料が補助されるのか、疑問を抱く声もあります。リンク先Facebookd動画日章学園九州国際高等学校について
今後、この流れが大学にも波及する可能性がありますが、その際は、まず、国立大学の授業料引き下げや奨学金制度の改善が優先されるべきだと思います。無償化は負担軽減の一方で、学習意欲の低下や安易な退学を招くリスクもあります。教育政策の本質は、「誰もが等しく学び、成長できる環境づくり」であり、高校・大学に進学しなくても仕事ができる労働環境の整備や、必要に応じたリスキリング(学び直し)の仕組みを強化することも重要です。
※人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。リスキリングの制度としてぜひ利用してはいかがでしょうか・
無償化の是非を考える際には、「教育の公平性」と「財政負担」のバランスを見極め、より持続可能な制度設計を目指すべきだと思います。