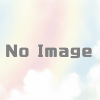差別のない沖縄へ!報道のあり方は適切か?

沖縄県は、多様性を尊重し、すべての人々が平等に暮らせる社会の実現を目指し、2023年3月に「沖縄県差別のない社会づくり条例」を制定しました。この条例は、公共の場やインターネット上における不当な差別的言動、特に外国人など本邦外出身者に対するヘイトスピーチの解消を目的としています。具体的には、差別的言動が確認された場合、審議会の意見を踏まえ、県が発言の概要や発言者の氏名を公表できる仕組みです。
そして2025年3月31日、県は初の適用事例として、インターネット上に投稿された2本の動画が不当な差別的言動に該当すると発表しました。これらは県内で撮影され、「中国人出て行けー」などと排除を扇動する内容を含んでいました。しかし、投稿者の所在が特定できなかったため、県は氏名の公表には至っていません。
このような状況の中、ある新聞社が独自調査に基づき、動画の作成者とされる人物の氏名を報道により公表しました。ここで、報道の在り方をめぐるいくつかの重大な問題が浮かび上がります。
まず指摘すべきは、プライバシーの侵害と名誉毀損のリスクです。個人の氏名を公表することは、その人の社会的評価に重大な影響を与えます。もし誤認があれば深刻な人権侵害となり、修復困難なダメージをもたらします。条例では、あくまで行政が審議会の意見を経て責任を持って判断する仕組みが整えられており、それを経ないまま、報道機関が独自に個人情報を晒す行為は、手続き的正義を欠いた暴走と見ることもできます。
さらに、氏名の公表によって生じる影響は本人にとどまりません。家族や職場関係者など周囲の人々にも波及的な被害が及び、新たな偏見や差別を助長するおそれがあります。それはまさに、差別をなくすために作られた条例の趣旨と矛盾する事態です。
もちろん、ヘイトスピーチは決して許されるものではなく、厳正な対処が求められる行為です。しかしその対処は、法と制度に基づく慎重なプロセスを経て行われるべきです。
一方で、報道機関側は「公益性」を根拠に、実名の公表を正当化する立場を取るかもしれません。確かに、社会にとって重要な問題に光を当てる役割は報道の根幹です。しかし、公益性が主張されるからといって、すべての手続きを飛び越えてよいわけではありません。
公益を名目に個人の尊厳を侵害することは、報道の自由の濫用に他なりません。
また今回、制度の側にも課題があることは否めません。条例における「不当な差別的言動」の定義や、「氏名公表」に至る基準は必ずしも明確とは言えず、恣意的な運用が懸念される余地もあります。このような曖昧さは、行政の萎縮や、逆にメディアによる“補完的正義”の暴走を招きかねません。制度を整えることと、報道機関が法手続きを無視することは、まったく別の問題です。
報道機関は社会の「番人」として、権力を監視する重要な立場にあります。しかしその影響力の強さゆえに、より高度な倫理性と自制が求められます。言論の自由と個人の権利、その双方をどう守り両立させるかは、民主主義社会の基盤に関わる問題です。
「差別を許さない社会」と「手続きを尊重する社会」は両立できます。むしろ、その両立こそが本当の意味での「差別のない社会」への道筋です。
正義感に駆られた独走ではなく、制度と倫理に支えられた冷静な対応こそが、私たちの社会にとって必要な姿勢ではないでしょうか。