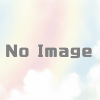さとうきびは島を守り、島は国土を守る!
皆様もご存知のように、サトウキビは誰が何と言おうと、沖縄県の基幹作物であります。生産量は、気象条件や農業経営環境の変化により、年によって増減があります。以下に、近年の生産量の推移を示します。
-
2018~2019年期 | 742,584トン
-
2019~2020年期 | 813,853トン
-
2020~2021年期 | 716,200トン
-
2021~2022年期 | 828,110トン
-
2022~2023年期 | 737,439トン
-
2023~2024年期 | 664,284トン
このように、令和3年~4年期(2021~2022年期)に82万8,110トンを記録した後、近年は減少傾向にあります。特に、令和5年~6年期(2023~2024年期)は66万4,284トンと、平年よりも少ない不作となりました。
この減少の要因としては、台風や干ばつなどの気象条件の影響が考えられ、合わせて、農家の高齢化や後継者不足といった課題も影響している可能性があります。
また、年間の出荷額はおよそ200億円。これにより、県内の製糖業や黒糖加工業が成り立ち、広範な雇用が生まれています。特に離島地域では、サトウキビ生産が地域経済と生活の基盤を支えており、収穫期には県内外からの季節労働者を受け入れることで地域の労働市場を形成しています。また、サトウキビは赤土流出防止やCO₂吸収といった環境保全の役割も果たしています。国の甘しゃ糖価格調整制度により、農家には安定的な収入が保障され、地域全体の経済の安定化にも寄与しています。これらの要素を含めた経済波及効果は、年間1,000億円から2,000億円に達すると試算されており、サトウキビは沖縄の農業のみならず、産業・雇用・環境・文化の多方面にわたって重要な存在となっています。
しかし、課題も山積しています。県内の製糖工場の多くは建設から50年以上が経過し、設備の老朽化が進行しています。例えば、うるま市の「ゆがふ製糖」では、老朽化に伴い中城湾港新港地区への移転を検討していますが、事業費が約300億円に上るとされ、国の補助が6割あっても、残りの資金調達が難航しており、事業主体も未定のままです。
ここで重要なのは、公費による巨額の整備が、本当に持続可能なサトウキビ産業の再生に直結するのかという点です。農家の減少、若年層の農業離れ、作付面積の縮小が進行する中で、高額な設備投資が将来にわたり十分に活用される保証はありません。過疎化が進む離島地域において、仮に製糖工場が最新化されても、操業に必要なサトウキビの供給が不足すれば、投資効果が限定的となり、税金の使途として適切だったのか問われることにもなりかねません。
また、2024年から施行された働き方改革関連法により、製糖工場でも時間外労働の上限規制が適用され、従来の長時間労働に依存した操業体制の見直しが求められています。これに対応するためには、労働環境の改善や省力化・自動化の推進が不可欠ですが、それにも多額の追加投資が必要となります。
このように、施設整備への公的支出が増加する一方で、サトウキビ産業全体の縮小傾向に歯止めがかからない状況下においては、単にハード面を整備するだけでは十分ではなく、人材育成や経営継承、販路拡大、農地集約化などの総合的な支援が同時に進められなければ、投資が空回りする懸念があります。
沖縄県では「さとうきび増産プロジェクト会議」を設置し、増産に向けた対策を講じていますが、持続的な生産体制の構築には、設備投資の是非も含めた戦略的・段階的な見直しが必要です。

特に、国境離島における定住者の安定的な生活にはサトウキビ農業と製糖工場の操業は欠かせません。「さとうきびは島を守り、島は国土を守る」──これは南大東島の大東糖業の煙突に書かれた文字ですが、その理念を次世代に繋いでいくためにも、費用対効果と将来展望を見据えた慎重な判断が求められています。