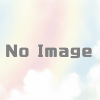県民の『そば』には豚肉が必要なのです!
沖縄県において、豚肉は単なる食材の枠を超え、長年にわたって「文化」として根付いてきました。琉球王国時代から、「鳴き声以外はすべて食べる」と言われるほど、豚は余すところなく利用され、生活のあらゆる場面に関わってきました。日々の食卓はもちろん、お盆や正月、清明祭(ウシーミー)などの伝統行事、さらには結婚式や法事など、人生の節目においても欠かすことのできない存在です。
たとえば、沖縄そばの出汁には豚骨やカツオが使われ、上に乗せる三枚肉やソーキの煮付けは「そば文化」の象徴とも言えるでしょう。中味汁(豚モツのスープ)やテビチ(豚足の煮込み)など、バリエーション豊かな豚肉料理は、県民の食生活の核をなしています。ラード(豚脂)もまた重要な素材であり、琉球菓子であるちんすこうの製造には欠かせません。ラードがなければ、あのホロホロとした口どけは再現できず、ひいては「ちんすこう君」などの文化的キャラクターも生まれなかったかもしれません。このように、豚肉は沖縄の「胃袋」を支えるだけでなく、伝統やアイデンティティとも深く結びついています。
危機に瀕する養豚業の現状
しかしながら、こうした食文化の基盤を支えてきた養豚業は、いま重大な転換点を迎えています。2024年現在、沖縄県内の飼養豚頭数は約18万4,500頭と、1973年以来の低水準に落ち込みました。わずか10年前には24万頭を超えていたことを思えば、極めて深刻な減少です。農林水産省の統計でも、20万頭を割り込んだのはおよそ半世紀ぶりとされており、県内の豚肉供給体制が根幹から揺らいでいることは否定できません。沖縄県畜産課公表データ:PDF
養豚農家の戸数も、2015年の285戸から2023年には195戸、さらに2024年には174戸と急激に減少。かつては家族経営の小規模養豚場が地域ごとに存在していましたが、高齢化や後継者不足、経営採算の悪化などが重なり、廃業を余儀なくされる例が相次いでいます。
養豚数18万4500頭、50年ぶり低水準 2024年沖縄県内 飼養農家数174戸で過去最少2024年7月31日 5:16 沖縄タイムス
飼料高騰という構造的課題
養豚業衰退の最大の要因のひとつが、輸入飼料価格の高騰です。近年、国際的な穀物価格の上昇、円安の長期化、地政学的リスクなどが複合的に影響し、トウモロコシや大豆などの飼料価格は過去10年でおよそ1.8〜2倍にまで上昇しています。大規模農場であれば一定のスケールメリットを活かせますが、規模の小さな農家にとってはコスト増に耐えきれず、養豚事業からの撤退を選ばざるを得ないケースが増えています。このような背景から、近年は大規模経営体による集約化も進んでいますが、県全体としての飼養頭数を安定的に維持するには限界があります。特に中山間地域や離島などでは、地理的制約から規模拡大が難しく、地域ごとの供給体制をいかに支えるかが喫緊の課題です。
母豚不足と再生産体制の危機
さらに深刻なのが、繁殖用の母豚の減少です。母豚は年に2回ほど出産し、一定数の子豚を産みますが、回数を重ねるごとに繁殖能力が低下するため、定期的な更新が必要不可欠です。沖縄県では現在、約17,000頭の母豚が飼養されていますが、そのうち毎年7,000頭程度の更新を確保できなければ、子豚の生産力が持続的に損なわれていく恐れがあります。こうした状況を受けて、沖縄県は養豚振興協議会と連携し、母豚導入に対する支援策を講じました。具体的には、県外からの母豚共同購入に対して、その購入費と輸送費の合計のうち50%を補助する制度です。本土では1頭あたり7〜8万円で購入できる母豚も、沖縄では輸送費を含めると12万円前後かかります。この支援制度は、農家の負担軽減と再生産体制の回復に一定の効果を上げました。
しかしながら、この補助制度は現状、単年度事業にとどまっており、母豚更新の安定サイクルを支えるには不十分です。現場からは「最低でも3年間以上の継続支援が必要だ」との声が上がっており、県も制度の延長に前向きな姿勢を見せています。今後は、予算措置の確保だけでなく、より繁殖効率の高い多産系統や原種豚の導入支援も並行して行うことで、生産性の底上げを図る必要があります。
沖縄の畜産「危機的な状況」 業界6者、支援求め県議会に請願書 飼料価格は高止まり、離農や飼養頭数の減少続く2025年6月25日 4:00 沖縄タイムス
豚肉文化を未来へつなぐ責任
沖縄の豚肉文化は、私たち県民の暮らしと心に深く根ざしています。これは単なる「食」の問題にとどまらず、風土、歴史、地域コミュニティの再生とも関わる重要なテーマです。養豚業の安定的な運営なくして、沖縄の食卓は成り立ちません。母豚導入補助は、その再建の入り口にすぎませんが、こうした支援を継続的かつ計画的に展開していくことで、持続可能な食文化と供給体制を築いていくことができます。
豚肉を守ることは、単なる産業保護ではなく、沖縄の文化と暮らしを未来へと繋ぐ行為に他なりません。県民の「そば」に、これからも美味しい豚肉が添えられ続けるよう、私たちには今、行動が求められています。

参考 DISCOVER NIKKEI「550頭の豚、太平洋を渡る」1948年の沖縄復興支援(ハワイから豚が送られた史実)が、豚肉文化の継承に果たした役割を文化史的観点で追跡